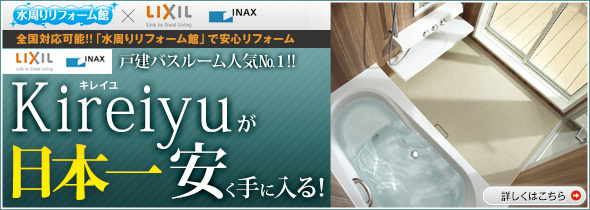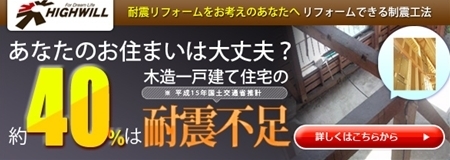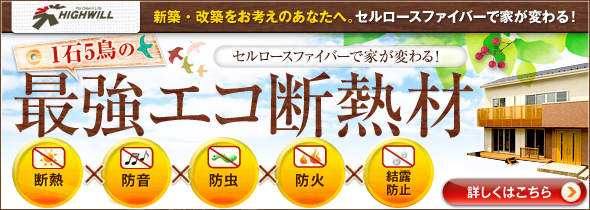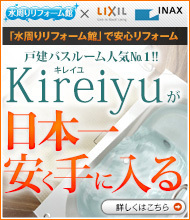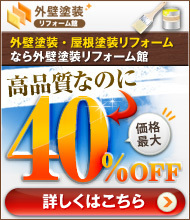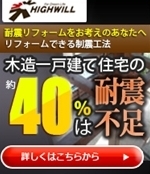ビジョン」をとりまとめ、5月31日に公表。政府の骨太の方針に盛り込んで
ゆく見込みだ。
うことが時代の要請ととらえ、超長期住宅の普及を目指すもの。レポートで
は「超長期にわたって循環利用できる質の高い住宅」と定義している。
共通書式でまとめる「家歴書」の整備を中心的な施策と位置づけ、既存住宅
の流通をうながすとともに、消費税や住宅税制のあり方、新しい住宅ローン
枠組みの検討などを盛り込んだもので、来年度の立法措置を目指す。これか
らはマンション選びも「200年」の視点にたって選びたい。
イフ住宅)のことで、「200年」というのは、住宅のロングライフ化を象徴
的に表す言葉として使われている。
77年に比して著しく短いことが問題視されてきた。環境問題や社会の成熟
などを背景に、ストック型社会への転換が求められ、2006年の住生活基本
法の制定を機に、ストック重視政策へ転換しはじめた。
が約3分の2程度に軽減することが予測されているほか、産業廃棄物は年間
約1000万t(東京ドーム5個分の容積)削減し、また建設時や住宅使用時の
省エネルギー性能の向上によりC02削減にもなる。つまり住宅が社会資産と
して認識されるようになれば、環境への負荷を最小限にとどめつつ、経済社
会の持続的な発展を実現できるというわけだ。
(インフィル)が分離され、スケルトンについては耐久性・耐震性、インフ
ィルについては、可変性が確保されていること」「次世代に引き継ぐにふさ
わしい住宅の質(省エネルギー性能、バリアフリー性能)が確保されている
こと」「計画的な維持管理(点検、補修、交換等)が行われること」「周辺
のまちなみとの調和が考慮されていること」が挙げられている。
価システム、金融システムの変革など、社会基盤の構築が必要で、国民の意
識改革も迫られている。欧米の古い町並みでは100年を超える集合住宅も少
なくないが、ようやく日本もそういった成熟した社会へ歩みをすすめはじめ
たといえるだろう。
需要が増えており、現状は3:1の割合で新築割合がまだまだ高いといえま
すが、今後10年でこの割合は逆転するだろうといわれております。
なども加われば、悪徳業者への牽制にもなりますし、職人の教育にも良い影響
がでるのではないでしょうか。非常に楽しみです。